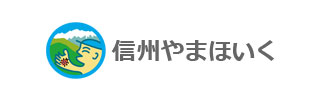子どもの居場所の選択肢の一つとして、フリースクールもあることを伝えたい
2023年に行われた「信州型フリースクール認証制度検討会議」の委員として参加していた成澤乃彩さん。当時は信州大学教育学部の4年生で、自身の不登校の経験を伝えることが、子どもたちにとっての多様な学びの選択肢の確保につながるのではないかと、自ら志願しました。現在は、都内で大学院1年生として学びを深める成澤さんに、思いを語ってもらいました。
一歩踏み出したら、自分の世界が広がった

私が不登校になったきっかけは、自律神経の不調で起こる「起立性調節障害」でした。中1の5月に突然倒れてから、原因が分からないまま、朝起きられない、学校へ行っても具合が悪くなる、ということが続きました。学校は好きでしたし、その頃は、勉強も友達も、なんというか、学校という世界が全てだったので、つらかったです。中2の時に、少し体調が安定してきたのでしばらく登校してみたこともあったんですが、なかなか難しくて、結局不登校の状態に戻ってしまいました。
中3になって、進路について考えるようになりました。将来やりたいことはなかったんですが、いずれは社会に出なきゃいけないという思いと、友達や仲間と一緒に学生生活を送りたいという思い、そして、ここで一歩踏み出さないとずっと引きこもりのようになってしまうのではないかという不安がありました。夏ぐらいから動画などを見ながら勉強を始めたんですが、なかなか思うようにいかなくて。その頃に、中学校で別室登校ができることを知って、これしかないと思いました。正直、最初は行きづらかったですが、少しずつ長い時間学校にいられるようになりました。別室を担当している先生が、勉強だけではなく、私の知らないことをいろいろと教えてくれて、「こういう先生っていいな」と思ったことが、先生になりたい、そのために大学に行きたいという新たな目標になりました。
高1のときは時々、体調を崩すこともありましたが、大学進学という目標があったのが良かったと思います。地元の上田市内の高校に通いながら、勉強以外のことにも意欲的に取り組みました。例えば、「生徒が主体性を育む交流会」(県校長会と県教育委員会が主催し、全県から募った高校生と大学生が交流する会)の実行委員を務めたり、地元の子ども食堂のボランティアをやったり。さまざまな人たちと出会って、自分がこれまで見ていた世界は狭かったと感じました。
不登校の子どもたちのために、真剣に取り組んでいる大人がいる

大学に入学したのは2020年の春。コロナ禍と重なり、なかなかリアルな場での活動は制限されてしまいました。それでも、地元だけではなく、長野市や松本市の子ども食堂にボランティアで参加し、そのつながりで、不登校の経験を話す機会もありました。そこで、自分の経験を話すことが、不登校について知ってもらうことになると感じたんです。3年生の春休みに、「信州型フリースクール認証制度検討会議」のことを偶然フェイスブックで見ました。「不登校の経験者の声もあったほうがいいのでは」という投稿者の声に後押しされるようにして応募し、4年生の4月から委員として参加しました。行ってみたら、大学生は私一人だけでびっくりしましたが…でも、不登校の子どもたちのためにこんなに真剣に取り組んでいる大人がたくさんいることがとても嬉しかったです。委員として参加していたフリースクール運営者の方にお願いして、何カ所か見学にも行くことができました。それがフリースクールとの最初の関わりです。フリースクールは、自分が不登校だった頃に母から「こういう場所があるらしいよ」と聞いてはいましたが、当時は「学校に行きたい」という気持ちが強くて、それ以外の選択肢を考えられなかった。小学校の頃に不登校気味の子がいて、周りの反応なども見ていたので、不登校に対する印象も正直あまりよくなくて、自分がそうなっていることを受け入れられなかったのかもしれません。大学でも、周りに不登校の経験があるという人はいませんでした。
私が会議に出たり、フリースクールに行ったりしているのを、大学の同期や後輩に話したら、興味を持ってくれる人もいて、それが「ゆい」というサークルを立ち上げるきっかけになりました。大学4年生の冬で、卒業間近だったんですが、フリースクールの運営者と学生をつなげることができたらいいなと思って、友人と2人で始めました。
不登校になったのは、本人のせいでは絶対にない
大学では不登校や子どもの貧困など、興味のあることに取り組むことができて、もっと研究したいという思いが湧きました。私の研究したいテーマを専門にしている先生がいることを知って、大学院への進学を決めました。教職大学院なので、実習先は自分で希望して、サポートルーム(校内教育支援センター)にしました。実習が終わってからも週に1回、支援員として入っています。サポートルームには、少し教室に行ってみたいという子もいれば、ずっとサポートルームにいたいという子もいて、皆それぞれです。保護者の方に話を聞く機会もあり、抱える思いについても知ることができました。
大学院では、全国各地でどのような取り組みが行われているかということも調べています。あと1年、実践を経て、長野に戻ってきて、その知識や経験を生かしていければ。まだまだフリースクールの存在自体を知らない人もたくさんいると思うので、子どもの居場所の選択肢の一つであることを、子どもたちや保護者の方に情報として提供できる、必要な時に橋渡しができる先生になりたいと思っています。

私が不登校だった時は、自分が一生、外に出られないんじゃないかとか、死んだほうが楽になれるんじゃないかと思ったことも正直あります。こうなった原因はすべて自分にあると、思い詰めていたんですよね。でも、絶対そうではない。今は、子どもがそんなふうに追い詰められている社会がおかしいんじゃないかと思います。そんな社会を変えていきたいし、変えようとしている人がいっぱいいることを知ってほしい。もし今、学校に行けない子がいたら、学校がすべてではないので、違うところに一歩踏み出してほしい。そこには学校にはいないような面白い人や、自分に合う人が絶対にいます。未来は明るいし、希望を持ってほしいと伝えたいです。