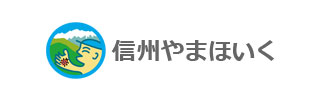現況について
-
不登校児童⽣徒を取り巻く状況はどうなっていますか?
本県の不登校児童⽣徒数(⼩中学校)は以下のとおりです。
R4: 5,735⼈(H29: 2,587⼈)→ 5年間で2.2倍に増加、過去最多
児童⽣徒1,000⼈当たりでは36.9⼈で全国(31.7⼈)を大きく上回り、 全国で5番目に高い割合 -
フリースクール等⺠間施設はどのような役割を果たしていますか?また、状況はどうなっていますか?
フリースクール等⺠間施設(以降「フリースクール」という。)は、増加する不登校児童⽣徒等に対する多様な学びの場(学びの選択肢)の確保のために重要な役割を果たしている一方で、運営基盤が脆弱なこと等の課題を抱えているケースが散⾒されます。
なお、県で把握している県内⺠間施設の利⽤者は以下のとおりです。
…R4: 396⼈(H29: 94⼈)→5年間で4.2倍に増加、過去最多
制度の趣旨等について
-
信州型フリースクール認証制度のポイントは何ですか?
本制度のポイント(主な特徴)は以下となります。
- 「出席扱いとなる利⽤児童⽣徒がいることは原則問わない」
- 「地域・社会資源(⾃然・歴史・⽂化・⼈材)の活⽤を推奨」
- 「居場所と学びの各々の役割に応じて認証を類型化」
- 「研修、情報発信、連携促進等、運営をトータルで⽀援」
- 「創設以降も、こども・若者と共に育てる制度を目指す」
-
信州型フリースクール認証制度の趣旨や、フリースクールを認証する意義は何ですか?
フリースクールが、子どもたちの置かれている状況やその希望をくみ取り、不登校児童⽣徒等の学びを保障し、社会的⾃⽴等を⽀援していくためには運営の安定化が必要です。
そのために、「信州の豊かな環境を活かしながら取り組む多様性に富んだ学びの場」として、一定の基準を満たすフリースクールを県が認証して必要な⽀援を⾏います。 -
本制度はどのような過程で認証されますか?
フリースクールからの認証申請を受け付け、書類審査・現地確認等、一定の⼿続きを経た上で、認証懇談会による有識者の意⾒を踏まえて認証します。
-
信州型フリースクール認証制度により、⻑野県が目指す姿は何ですか?
まずは、不登校児童⽣徒等、必要な児童⽣徒が過度な負担なくフリースクールに通えるよう、身近な場所で「多様な学びの選択肢(場)が増えること」、また「そうした学びの場の情報が広く県内に⾏き渡っている状況」を目指します。
次の段階としては、多くの市町村に認証フリースクールを広げ、「フリースクール職員の⽀援体制、居場所や学びの質が担保されている状況(全体の底上げ)」を目指します。 -
認証懇談会はどのような方々で構成されますか?
学識経験者、教育関係者、NPO⽀援団体等により構成されます。
-
「子どもの社会⾃⽴」の具体的な姿をどのように考えていますか?
⾃⽴の在り方は一様ではなく、一⼈一⼈の置かれた環境や状況により判断が異なるものですが、他者と連携・協働しながら社会に参画している姿と捉えています。
本制度による居場所や学びの場の確保・充実に加え、本県や様々な関係機関によるこども・若者への⽀援施策全般を通じて、将来的な引きこもり、ニートや発達障がい等の特性への理解や⽀援の不⾜によって、⻑期に悩みを抱える県⺠の増加に⻭⽌めをかけることを目指しています。 -
憲法第89条では、「公⾦その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使⽤、便益若しくは維持のため、⼜は公の⽀配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを⽀出し⼜はその利⽤に供してはならない。」とありますが、これを踏まえて⾏政によるフリースクールへの⽀援はどう整理していますか?
県が設定する基準を満たす⺠間施設を信州型フリースクールとして認証し、認証を受けた施設に対して予算の範囲内で財政⽀援を⾏う仕組みです。
この認証⼿続きを経ることで、公の⽀配に属するものとして整理しています。
また、認証の段階での判断のほか、予め要綱等で示す一定の要件により認証の取消を可能とすることで、厳正な制度運⽤を⾏うことができるものと判断しています。 -
他の都道府県や市町村では、寄付⾦や助成⾦、基⾦等により時限付きのフリースクール⽀援制度が⾒受けられます。認証制度はいつまでの事業ですか?また、 認証を一度受けた際の有効期限はありますか?
信州型フリースクール認証制度は、児童⽣徒にとって多様な学びの場の確保と保障を目指すものであり、制度の必要性は現在の社会や学校を取り巻く環境等から⽣じているものです。そのため、現段階で時限的(モデル的)な制度とすることは想定していませんが、取り巻く環境等の変化や国における⽀援の検討状況なども鑑み、制度の継続を判断していきます。
認証の有効期限は、認証⽇から3年間であり、更新する場合は有効期限の3か⽉前までに更新の申請が必要となります。 -
市町村(学校組合)⽴の学校においては、市町村(学校組合)⽴の責任のもとで不登校児童⽣徒への⽀援の充実を図るべきで、県がその肩代わりをして⽀援するのは、どのような意図がありますか?
義務教育に責任を負う市町村教育委員会が、不登校児童⽣徒等に対する学校以外の場での学習等への⽀援を推進する役割を担っており、教育⽀援センターの運営等に取り組んでいますが、同時に、県並びに県教育委員会においては、市町村間の情報共有や広域的な観点からの⽀援の推進に取り組む必要があると認識しております。
本県では、居住地の(在籍している学校が所在する)市町村を越えてフリースクールを利⽤している児童⽣徒が一定数⾒受けられ、広域的な観点で⽀援の必要があると判断されることから、県教育委員会と協働して本制度を推進するものです。 -
信州型フリースクール認証制度とその財政⽀援については、どのような規定(要綱等)で構成されますか?
本制度は主に「認証制度要綱」 及び「補助⾦交付要綱」で構成されます。各々で申請が必要であり、補助⾦交付を受けるためには認証フリースクールであることが前提となります。
補助⾦交付に関するQ&Aは別途整理します。 -
提出する認証申請書は、利⽤者等一般向けに公開予定ですか?
申請書そのものは公開対象ではありませんが、認証制度要綱の第8(認証書の交付等)第3項に基づき、認証された場合は、利⽤者等の利益となり得る一部の申請情報についての公開を想定しています。
認証申請について
-
認証対象となり得る「フリースクール等⺠間施設」とは、どのような事業者・団体ですか?
学校外において、不登校等児童⽣徒等に対して学びや社会的な⾃⽴に向けた⽀援を提供する⺠間施設をいい、その運営者は法⼈・個⼈を問いません。本制度ではこれら施設をまとめて「フリースクール」と整理します。
フリースクールという名称を含む事業のみに限定しませんが、独⽴した事業会計により会計処理されていること、特定の児童⽣徒のみを利⽤対象としていること、平⽇の⽇中に開所されている必要があること、在籍校との連携が図られていること等、不登校児童⽣徒等への⽀援を主目的とする事業者・団体が対象となります(詳細は認証基準を参照)。
このため、「学習塾や予備校、インターナショナルスクール、放課後等デイサービス」などの趣旨や目的が異なる者は原則対象外となりますが、上記基準を満たす場合は個別にご相談ください。 -
放課後等デイサービスを運営していますが、事業外の時間帯に不登校児童⽣徒への居場所等提供を⾏っています。具体的にはどのような場合に本制度の対象となりますか?
いずれの団体も全ての認証基準を満たす必要がありますので、確認書等の申請様式により各基準の充⾜状況を各⾃ご確認ください。その際、ご不明点がありましたら予めメール等により個別にお問い合わせください。
-
フリースクールを利⽤する「不登校児童⽣徒等」はどこまでが対象ですか?
病気や経済的な理由による者を除き、何らかの⼼理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にある義務教育段階の児童⽣徒をいいます。
現在の⽂部科学省の定義である、在籍校の⻑期⽋席者(年間30⽇以上の⽋席者)に必ずしも該当する必要はありません。 -
「学び」とは、どのような学習範囲を指しますか?
子どもの社会的⾃⽴を目指した、一⼈一⼈に応じた学習活動(教科等学習や体験活動)をいい、学習指導要領に関わる項目を含みます。
信州の豊かな環境や地域に根差した学びを実践するため、地域・社会資源(⾃然・歴史・⽂化・⼈材)の活⽤を推奨します。 -
地域・社会資源(⾃然・歴史・⽂化・⼈材)の活⽤とは具体的に何を示しますか?
例えば、野外活動、観察、⼯作、芸術活動等を含んだ総合的な学びの活動であり、対象を課題とした問題の解決や探究活動を想定します。例示としては、以下のような活動が挙げられます。
- 地元の企業と連携した職場⾒学・体験等を通じた学び
- 各分野の講師を招聘した専門的・実践的な学び
- 農作物の栽培等を通じた、植物の⽣育や食⽂化・土と触れ合う学び
- 地域内外における、遺跡等の歴史を学ぶ活動
-
社会的⾃⽴等に向けた相談⽀援の場とは、どのような場を指しますか?
悩みを受け⽌める相談や⽀援に対応する職員が在所することで、利⽤する児童⽣徒が存在感・⾃⼰肯定感を認識することができ、精神的に安定できる居場所を指します。
居場所としてフリースペース等の名称を含む事業のみに限定しませんが、⼼理的安全性の確保や社会的⾃⽴・⽣活⾃⽴を促す場が想定されます。 -
認証申請要件を満たさないこととなる「5年間に、運営者及び学びや居場所の提供者が、福祉や教育関係の法令等に違反して刑事罰や⾏政処分を受けていないこと」のうち、福祉や教育関係の法令等は何を指しますか?
例えば、児童福祉法、児童虐待防⽌法、児童買春・児童ポルノ禁⽌法、⻑野県子どもを性被害から守るための条例、教員等による児童⽣徒性暴⼒等防⽌法、学校教育法、社会教育法等(以上、通称含む)を指します。
-
認証申請要件を満たさないこととなる「運営者や職員への著しく高額な⼈件費の⽀出」とは、どこまでを指しますか?
報酬や謝⾦等が定款(⼜は団体の給与規定等)で規定している額の限度を超えていないか、実際の勤務実態や業務量、収益状況を勘案して、社会通念上著しく高額でないかという観点で判断します。
同種の団体等と⽐較して高額と⾒受けられる場合は、別途詳細な説明を求めるほか、公平性の観点から、認証による⽀援やこれに基づく公⾦⽀出が望ましくないと判断し、認証申請を受理しない⼜は認証しない場合があります。 -
認証申請要件を満たさないこととなる「営利が主たる目的である活動」とは、どこまでを指しますか?
利⽤者への高額な利⽤料設定など、公共の福祉の観点からかけ離れる著しく営利本位な場合は、認証による⽀援やこれに基づく公⾦⽀出が望ましい活動でないと判断します。一方で、認証申請に係る活動の事業収支は必ずしも⾚字である必要はありません(収支が黒字か⾚字かは問いません)。
-
学校や宗教法⼈等は認証申請が認められますか?
本制度の趣旨が学校以外の場への⽀援であるため、学校教育法(第1条に定める学校のほか、第124条・第134条による専修学校や各種学校を含む)に規定する学校は対象外となります。
また、宗教法⼈については、「教義をひろめ、儀式⾏事を⾏い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」とされていますが、中⽴性の観点から政治的活動団体と同様に対象外となります。 -
公教育者(現役の教員・公務員等)が団体の運営に関わっている場合は、申請が認められますか?
国や地方公共団体の規定の範囲内、⼜は、当該団体の運営に公務として携わっていない場合であれば、認証対象になり得るものとします。
-
親の会は、申請が認められますか?不登校当事者(子)が常時参加していれば認められますか?
不登校児童⽣徒等の保護者同⼠の相互交流や情報交換、勉強会等の場(いわゆる親の会)については、常設性の観点からも、活動の主旨からも、申請者の子とともに参加している場合を含めて申請対象外となります。一方で、親の会の活動を否定するものではなく、そうした団体と連携しながら、フリースクールが保護者への相談対応を含めて⽀援していることは重要と捉えています。
-
認証の取消があった場合、認証の再申請までは、実績となる1年間の活動が必要と理解してよいですか?
実績は取消の有無に関わらず判断されますが、認証の取消事由が悪質な場合は、再申請及び再認証が可能かどうか⾃体について個別に判断することとなります。
なお、認証を受けた者(運営者を含めて⽀援に関わる全職員)が、⽀援対象者への体罰や虐待、⼈権侵害⾏為等に関する特に重大事案に関与した事実により申請要件を満たさないことが判明した場合は、認証懇談会での意⾒を聴取した上で、認証を取り消す場合があります。また、この場合、取り消しをした⽇から起算して1年間は再度の認証申請ができないほか、当該期間は活動実績期間に含めないこととします。 -
認証制度要綱第4(2)の⾏政処分とはどのような処分を想定していますか?また、性加害等を⾏った者は過去5年間の処分に関わらず永年要件外となりますか? これらを含めた過去の法令違反等の事実認定はどのように⾏いますか?
⾏政処分としては、事業停⽌等を想定しています。
性加害については、同要綱第4(1)の規定により、過去全ての事案が対象となります。
違反等の事実については、申請者による当初の申告(誓約)に加え、認証審査時の現地調査や補助⾦監査等により確認予定です。また、今後は、国が検討を進める⽇本版DBS(犯罪歴等がない旨の確認制度)の本制度への関連付けなどを⾒据え、その動向の注視してまいります。 -
なぜ「居場所⽀援型」と「学び⽀援型」に類型化されているのですか?
不登校には初期段階、中間期段階、回復期段階等と段階や場⾯ごとの対応が必要とされています。
このため、⼼の休養(エネルギーの充填)のための居場所を必要とし、再び学習意欲を引き出す等のための⽀援を⾏う土台(基盤)となるような場を「居場所⽀援型」とし、これに加えて、⽐較的高い開所頻度により、学習活動等を積極的に⽀援する場を「学び⽀援型」と類型化し、各々で認証します。
なお、2つの型を同時に認証することは想定していません。 -
「居場所⽀援型」と「学び⽀援型」の要件の主な違いは何ですか?
大まかな相違点については、以下のとおりです。
- 「居場所⽀援型」は相談⽀援がなされており、週1回以上の開所が必要(学びの要素が含まれていても、対象となり得る)
- 「学び⽀援型」は相談⽀援に加え、⽐較的多くの時間の学びの⽀援がなされており、週3回以上の開所、教員免許取得者の配置、希望する利⽤児童⽣徒等がいる場合の在籍校での出席扱いが必要
※ 詳細の要件は、制度要綱における認証基準を参照ください。
-
同系列の団体(代表が同一)が県内に複数の施設を有して活動を⾏っている場合は、各々の施設で認証が認められますか? 県内に⽀部(店)の施設がある場合(県外本部(社))は、認証が認められますか?
同一団体であっても、対象施設が別々に所在し、各々で事業を実施している場合は、それぞれの施設において認証申請・認証取得は可能ですが、会計(経理)処理は別々で管理されている必要があります。
県外に本部(社)がある場合も、県内に⽀部(店)の施設がある場合は、上記と同じ考え方により認証申請は可能です。 -
県内に施設が所在するが、利⽤者が施設外(⾃宅等)からWEB等の通信端末により参加するような場合も認証が認められますか?
在宅学習⽀援を専門としている施設は、本制度では認証対象外となります(本制度ではホームスクールやホームエデュケーションは⽀援対象としていません)。
上記以外では、一時的な通信端末の利⽤を否定しませんが、通所による体験活動等の必要性を踏まえ、在宅学習のみの利⽤者については、認証基準となる利⽤児童⽣徒数の算定からは除外する必要があります。 -
基準を満たす児童⽣徒の「利⽤」をどう整理して扱えば良いですか?(体験利⽤者など)
本制度においては、以下の場合は原則利⽤者としての実績には含まない整理としますが、個別事情があればご相談ください。
- 利⽤登録のみ(通所実績なし)の場合
- 正式に⼊所していない体験利⽤の場合
- 1⽇当たり4時間未満の利⽤が常態化している場合
-
認証申請するフリースクールの単位で、利⽤者が複数⼈(2⼈以上)利⽤していることが要件ですが、年度の途中で在籍校へ復帰したこと等により要件を満たさなくなるような場合は認証申請できませんか(⼜は認証取消となりますか)?
申請⽇時点で要件を満たしている必要がありますが、申請年度内に2⼈以上の利⽤とならない⽉・⽇があっても直ちに要件外とはなりません。
ただし、本制度は、一定程度の規模(要件)によって⽀援に必要な職員を確保し、不登校児童⽣徒の受け皿となっているフリースクールを継続的に⽀援するものであるため、年度を通して⼈数要件を全く満たさなくなったような場合は、認証の取消(⼜は返上)が⽣じることとなります。
-
「不登校への⽀援について専門的な知識・経験をもっている」とはどういう職員ですか?
不登校の要因や背景によって⽀援の在り方が変わります。要因や背景を的確に把握し、アセスメントにより導き出された⽀援計画や⽀援方針等(それぞれの児童⽣徒に応じた目標や取組方針)をフリースクール運営者(⽀援者)・保護者・在籍校との間で共有し、目標や方針に照らして、児童⽣徒の状況を確認しながら⽀援が⾏える職員が求められます。
-
教員免許の取得とは、具体的にどのような種類まで対象ですか?現在は保有していない場合(過去に失効)でも問題ないですか?
⽀援する利⽤者の年代を問わず、幼稚園、⼩・中学校、高等学校、特別⽀援学校等のいずれの教員免許も対象となります。
過去に取得したものも対象ですが、教育職員免許法第10条の規定により、教育職員免許状が失効している者、⼜は同法第11条の規定により、教育職員免許状を取り上げられた者は対象外です。 -
教員免許の取得を要件としているのはなぜですか?
利⽤児童⽣徒の学びの充実に向けた専門的で幅広い学びや個別⽀援を、現状においてできる限り客観的に担保するためであり、ボランティア職員が教員免許を取得している場合も要件を満たします。
なお、県で今後実施(構築)を予定する研修プログラムの受講を当該要件に置き換えることについて、今後の制度変更の中で検討予定です。 -
特定のスタッフ1名(教員免許取得者)が複数のフリースクール等⺠間施設に⽀援者としている関わっている場合、それぞれのフリースクール等⺠間施設でスタッフとして申請してよいでしょうか?
運営費⽀援が⼈件費を含む主旨を踏まえると、望ましくありません。
ただし、特定の児童⽣徒が複数のフリースクールを利⽤し、⽀援にあたって複数の施設間で連携・調整が必要と判断され、特定のスタッフが施設間をまたいで⽀援する必要が⽣じている場合、スタッフの経費を按分して算定してください。
-
認証要件ではないが、認証申請時に報告する必要があるとされる保有資格は、どのようなものですか?
参考として、例えば以下のような資格等を保有している場合には申請時に報告してください。
- 臨床⼼理⼠、公認⼼理師、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠、作業療法⼠、児童発達⽀援管理責任者、サービス管理責任者、⾃然体験活動指導者など
-
認証要件として、スタッフの資格等に「対話を重視した伴走的なものであり、熱意を有していること」とありますが、具体的にどのようなことですか?
不登校⽀援に対する熱意に加え、使命感・誇り、愛情や責任感などを持ち、本⼈と⽀援者が継続的につながりながら、子ども一⼈一⼈の学びを最大限に引き出し、主体的な学びを⽀援する活動を想定します。
また、変化の著しい社会や教育分野で適切に対応するため、常に⽀援者⾃身が学び続けて向上⼼を持つことも求められます。 -
「週1⽇以上、平⽇の⽇中時間帯に開所していること」については、具体的な指定はありますか?また、当該時間帯に加えて土曜・休⽇⼜は夜間に開所している場合は⽀障がありますか?
不登校児童⽣徒の受け皿となる必要があるため、少なくとも学校同様の平⽇の⽇中時間帯での開所が原則必要です。
規則正しい⽣活リズムの定着が大切ですが、個々の利⽤者に沿った柔軟な対応も求められるため、具体の開所時間の指定はしないものの、1⽇当たり4時間未満(休憩時間は除く)の開所の場合は、本制度の開所⽇数に加えられません。 -
定期的な週1⽇の開所ではありませんが、定期に数⽇間まとめて開所し、年間総⽇数では週1⽇の開所に相当します。週1回開所と考えてもよいでしょうか?
本制度では、原則平⽇⽇中に週1回以上の定期開所を要件としています。
一方で、一定の期間において週1回以上の開所相当と判断できる場合(総合的に⽀援内容が認証基準を満たしていると認められ、児童⽣徒の⽀援のために柔軟な取り扱いが必要である場合等)は、対応できる可能性がありますので、個別にご相談ください。
-
1⽇当たり4時間以上(休憩時間は除く)の開所の場合に限り、本制度の開所⽇数に加えるとありますが、利⽤者の利⽤時間もこれによりますか?
本制度は、認証を前提としたフリースクール運営費(職員⼈件費)への⽀援であることから、一定程度まとまった時間として、職員が対応する「開所時間」が4時間以上という要件を満たすことが必要です。
利⽤者の「利⽤(滞在)時間」は必ずしもこれによらず、児童⽣徒の利⽤に不便が⽣じないよう柔軟な対応を否定いたしませんが、施設全体で開所と利⽤の時間乖離が⻑期間続く際等は状況を詳しく確認させていただく場合があります。 -
「1年間の活動実績」には、現在の前身となる運営団体での活動を含めても良いですか?
以前の活動が別事業ではなく、運営方針・⽀援内容等が大きく変更されていない場合は、期間の実績に含まれることがありますので、個別にご相談ください。
-
福祉事業所(福祉法⼈)で、不登校児童⽣徒を当年度1年間受け⼊れてきました。次年度から別事業(別会計処理)で対応しますが、当年度分は実績に含まれるでしょうか?
以前の活動が別事業ではなく、運営方針・⽀援内容等が大きく変更されていない場合は、期間の実績に含まれることがありますので、個別にご相談ください。
-
活動実績となる1年間が、年度の途中で経過した場合には、その時点から認証申請は可能でしょうか?
認証申請⽇の時点で1年間(開所⽇、活動開始⽇のいずれか遅い⽇から起算)の実績を満たす必要がありますが、申請募集は年間2〜3回程度の期間に分ける予定ですので、これに間に合う場合は認証申請可能です。
詳細は⼿続きフロー(申請の流れ)を参照ください。 -
在籍校との「定期的に連絡」とは、どのような頻度ですか?
フリースクール利⽤児童⽣徒の出⽋や、⽣活・学びの様子等については、⽉に1回程度の頻度での情報共有を想定していますが、在籍校のほか、利⽤児童⽣徒・保護者の意向なども踏まえてご対応ください。
-
在籍校との「⼗分な連携・協⼒」とはどの程度ですか?
⽀援計画(個々の利⽤児童⽣徒に応じた目標や取組方針)と目標や方針に照らした状況を定期的に共有することを想定しています。
-
在籍校から当施設での活動報告と評価を求められました。形式や様式はありますか?また、評価はどのように記したらよいでしょうか?
まずは、在籍校が求めている理由・目的と内容をご確認いただき、原則は在籍校から求められている形式や様式に応じてください。形式や様式がない場合には、本制度の参考様式を使⽤してください。
評価の仕方については、不登校児童⽣徒の学びのサポートガイド「はばたきVol.2」(⻑野県・⻑野県教育委員会、県HP: https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/shido/index.html)を参考に、子どもの学びの姿や過程を⾒取り、児童⽣徒が⾃らの活動を振り返り、次の活動に向かうことができるための評価を大切にしてください。 -
在籍校との連携・協⼒について、⻑野県教育委員会との連携は取れていますか?県教委が本制度を理解し、県内の市町村教委等に周知されているでしょうか?
市町村(市町村教委等)には、学校内外の⽀援機関による相互の連携推進等を図るため、本制度の周知とともに、⺠間施設とのスムーズな連携に理解・協⼒をいただくよう、知事部局(県⺠⽂化部)と県教委との連名により依頼⽂を発出(R6.1⽉)しています。
-
⽀援計画等を策定・共有するとありますが、⺠間施設は少ない⼈数でやりくりしており、在籍校による積極的な関与が必要と考えます。これら事務の簡略化は可能でしょうか?
利⽤児童⽣徒の⽀援計画等については、形式や様式がない場合には、本制度の参考様式を適宜使⽤して策定いただきますが、原則省略はできません。
なお、在籍校で策定している⽀援計画等の共有があり、⺠間施設の役割や⽀援内容についての記述がある場合はこれを参考にするなど、⽀援機関相互の連携により柔軟に対応ください。 -
どこまでの範囲の情報発信が要件ですか?
個別の状況にもよりますが、明確かつ積極的な施設等情報の発信がなされていることが要件であり、周辺住⺠や限られた保護者等へのチラシ配布、⾃治体の広報紙等のみへの一時的・局所的な周知のみでは要件を満たさないものと整理しています。
情報発信に際しては、地方公共団体によるホームページ等への継続的な情報掲載により代えることができますので、必要に応じてご相談ください。 -
利⽤者負担の⾦額を「⽉額〇〇円」と示しています。年、⽇、あるいは時間、回数等でも示す必要がありますか?
情報の発信内容として、年額、⽉額、⽇額、回数、時間ごとに利⽤⾦額の設定がある場合には、それそれの⾦額、教材費等利⽤者の負担になる内容について、利⽤者への有益な情報発信の観点から、原則分かり易い方法で示していただくことを想定しています。
-
保護者の相談⽀援はどこまでの対応が必要ですか?
利⽤に際しての個別相談対応や、⽀援計画のやり取り以外に、アウトリーチ(家庭への訪問等)⽀援も想定されますが、本制度は後者を必須とするものではありません。後者のような相談⽀援を望まれる場合は、利⽤児童⽣徒の在籍する市町村や学校への依頼・相談を検討ください。
-
保健・医療・福祉・教育等の⽀援機関とは、どの程度連携して対応すれば良いですか?
利⽤者の在籍校を含めて連携が⾏われるように、⽇常的な⽀援機関間の連携が重要です。そのためには、⽀援計画(方針)作成・更新(修正)時に、児童⽣徒一⼈一⼈に応じた関係機関の協⼒部署及び担当者を明確にし、それら機関とも⽀援計画(方針)を共有するなど、個⼈情報の扱い(保護者の了解を得る等)には留意しつつ、可能な限りの個別対応をお願いします。
-
全ての児童が疾患があるわけではありませんが、多くの児童が発達障がいやアタッチメントの偏りがあったりします。そのような背景の中、医療との連携は検討されましたでしょうか?医療専門家の介⼊や連携に関して、今後検討されることはありますでしょうか?
県としては、医療機関と各⽀援機関(者)とが直接連携を図ることが重要と考えます。
なお、本県では、発達障害者⽀援法に基づく「⻑野県発達障がい情報・⽀援センター」(委託先︓信州大学医学部附属病院)を令和5年4⽉に設置(改組)し、医療分野に加えて教育・福祉とも連携を強化しており、本制度においても当該センターとの連携体制をさらに密にしてまいります。 -
本制度は、県教育委員会、市町村教育委員会、⼩中学校・高校等とどのような関係性になっていますか?県教育委員会の具体的な関わりと、市町村教育委員会や学校などとの関わりを教えてください。 また、学校関係者や市町村教育委員会の意⾒などは聞いているのでしょうか?
各教育委員会、在籍校、フリースクールを中⼼に、その出席状況や⽀援方針・計画等に関して共有・調整を図るなど、不登校児童⽣徒の⽀援機関(者)相互の連携促進が特に重要と考えます。
制度化に際しては、県教育委員会事務局の関係課とともに検討を進めたところです。また、検討状況については、令和5年度上半期から、市⻑会・町村会、市町村教委育委員会連絡協議会や⼩中校⻑会等で説明の上ご意⾒いただいたほか、県内のフリースクールや教育⽀援センター等を訪問する形で意⾒交換を実施してまいりました。 -
研修等を実施する際、県内のフリースクールへの情報発信(案内)を県にお願いすることは可能ですか?
これまでの県による訪問等で連絡先を把握しているフリースクールへのメール等によるご案内に限られますが、内容など個別にご相談ください。
補助金について
-
県内におけるフリースクール等⺠間施設の運営者であれば、補助⾦の申請は可能ですか?
「信州型フリースクール認証制度実施要綱」第6により信州型フリースクールとしての認証を受けており、かつ、有効な認証期間内(認証日から3年間で、更新可能)である者が補助(申請)対象者となります。
認証基準等の詳細は、認証に関する「制度Q&A」を別途参照ください。
-
本事業に従事する職員が本事業以外の業務を兼ねて従事している場合は、補助申請可能ですか?
本事業に係る人件費を明確に按分して算定することで申請可能ですが、方法などの詳細は個別にご相談ください。
-
国や地方公共団体等の他の補助⾦制度を活用している場合は、補助対象になりますか?
国や地方公共団体等による他の補助金等と補助対象経費が重複していない場合で、かつ、他の補助事業の定めにより他団体との併用が禁止されていない場合は、その併用を認めております。
補助金交付要綱の様式第1号及び第4号(交付申請時、実績報告時)における「別紙1及び2」を用いて算定いただき、ご不明な点があれば個別にご相談ください。
-
活動の事業収支がマイナス(赤字)である団体のみが補助対象となりますか?
本事業の趣旨は運営基盤の安定化や支援の充実です。必ずしも運営費の欠損額を補填するものではなく、活動の事業収支は赤字である必要はありません(収支が黒字か赤字かは問いません)。
ただし、営利が主たる目的である事業については、制度の認証対象とはなりません。
-
本年度のいつ頃から補助⾦の交付申請が始まりますか? また、年度途中で交付申請することは可能ですか?その場合は、年度途中からの事業が補助対象期間となりますか?
・補助金の交付申請は、以下のとおり年間2回に分けて行う予定です。要件を満たしており、これに間に合う場合は申請可能です。なお、申請開始の際は、メール等で通知いたします。
【前年度までに認証されている者】
第1次募集:7月頃予定 第2次募集:11月頃予定【当年度に認証された者】
第1次募集:8月頃予定 第2次募集:12月頃予定いずれにおいても、申請する年度当初に遡って申請対象といたします。
詳細は⼿続きフロー(申請の流れ)を参照ください。 -
認証区分の「居場所支援型」と「学び支援型」とで、補助⾦の上限額が異なるのはなぜですか?
「学び支援型」では、認証基準である開所日数の違い等により、支援に必要な人件費や活動費が「居場所支援型」と比較してより多くの費用を要することが想定されるため、補助上限額に差を設けています。
-
補助金の上限額はどのような根拠により算出されていますか?
補助上限額は、県内フリースクールへのこれまでの調査、聞き取り等を踏まえて算出(※)しています。
(※)一部FSの経費のうち、人件費や活動費(外部人材への謝金等)の実績が根拠。
-
補助金の交付により、利用者(家庭)がフリースクールへ支払う利用料等の負担は減少することになりますか?
本事業は運営経費への支援のため、直接的な利用料負担の軽減措置ではありませんが、利用者が運営経費の一部を負担している場合、本事業による継続的な支援によって将来的にフリースクールの支援内容充実や利用料等に影響する場合があります。
-
運営費のうち「施設費」については、補助率が「定額」とはどういうことですか?
補助対象経費(賃貸料、光熱水費、広報費、学校連携費)の範囲内で、必要な経費の全額を補助します。
定額補助額については、施設の実利用人数に応じて、15人未満の場合は20万円、15人以上の場合は30万円としています。 -
どのような経費が補助対象経費に含まれますか?
補助金交付要綱別表(補助対象経費)に基づき、以下の経費が補助対象となります。経費ごとに補助金率が異なりますので、ご留意ください。
【運営費】
- 職員人件費(賃金、法定福利費)
- 外部講師等の支援者に対する謝金・旅費、職員の研修開催費、外部研修の参加費、学びに資する教材費、体験活動に要する経費(運動・工作・芸術・野外活動等のための備品購入費・修繕費、保険料、車両借上料、文化施設等入場料)
- 活動の場の賃借料、光熱水費、広報費、学校連携費(交通費、通信費等)
【安心・安全対策費】
- 活動の場の児童生徒の事故未然防止又は事故対応に要する経費(火災警報器、消火器、転落防止柵、自動体外式除細動器(AED)等)
- 活動の場の防犯対策に要する経費(録画機能付きドアホン、電子錠、防犯カメラ、センサーライト、刺股等)
- 活動の場の自然災害(地震や台風等)への備えに要する経費(家具等の転倒防止器具、防災セット(非常持出用の基本的なキッド)等)
-
消耗品や光熱水費、土地購入費などは補助対象経費とはなりませんか?
自宅等を支援の場としている運営者や他事業での使用など、様々なケースが想定されることから、以下については本事業の補助対象経費としていません。これら経費には、フリースクール利用者からの利用料や外部からの寄附金等の収入を充てる整理としてください。
- 軽微な額が多い消耗品費
- 運営施設用の土地や建築物の購入費や増築費等
-
補助対象経費となる「学びに資する教材費」はどのようなものが該当しますか?
例えば、各教科における教科書のほか、副読本、学習帳、ドリル、白地図等の図書教材が挙げられます。 また、各種統計、図やグラフ等についても、探求や発見につながる素材として有効と考えられれば、デジタル教材を含めて学びに資する教材に含まれる整理とします。
-
ピアサポーター等の学生ボランティアに交通費を経費で支給しています。運営費に含んでよいでしょうか?
支援者に対する旅費として、補助対象経費に含まれます。
-
フリースクールや居場所のスタッフ同士で学び合うような研修や講演会に参加するための交通費については、補助対象経費に含まれますか?
運営者やスタッフにとって、利用するこどもへの理解や支援の充実、フリースクールの交流につながるようなものは、「活動費(外部研修の参加費)」として補助対象経費に含まれます。
-
活動に使う体育館などの施設の利用料金は補助対象経費に含まれますか?
学びのための活動や居場所として必要と整理できるものは、「活動費(体験活動に要する経費)」として補助対象経費に含まれます。
-
PC機器等の通信端末は、補助対象経費である学びに資する教材費や体験活動に要する経費に含めてよいでしょうか?
在籍校や他の団体から配布される機器と重複するような場合は、その周辺機器等も含めて対象とならない場合がありますので、個別にご相談ください。
-
PC機器等の通信端末は、運営者やスタッフが運営のための事務の用途として使用するような場合でも補助対象経費に含めてよいでしょうか?
在籍校との連携(こどもの様子や出欠状況等の連絡・共有、個別支援会議の参加など)の用途が主であれば、PCの購入費やその通信費等は補助対象経費に含まれますが、詳細は個別にご相談ください。
-
運営費のうち「施設費」は、項目ごとに具体的にどのようなものが補助対象経費の対象になりますか?
- 「賃借料」については、活動の場の土地及び建物に係る経費が対象となります。
- 「光熱水費」については、施設の開所に必要な電気料金、ガス・灯油料金、水道等料金のうち活動の場に係る経費が対象となります。
- 「広報費」については、活動の場の広報(チラシ等の作成・印刷・発送費、新聞・雑誌・Web等の広告代、ホームページ等の作成・管理費、案内用看板の作成・設置費)に係る経費が対象となります。
- 「学校連携費」については、フリースクールを利用するこどもの在籍校との連携・協力(こどもの様子や出欠状況等の連絡・共有、個別支援会議の参加など)に係る経費(交通費、通信費等)が対象となります。
-
「安心・安全対策費」は、具体的にどのようなものが補助対象経費が対象になりますか?
対策のための備品・物品の購入費(簡単な取り付け費用を含む)を補助対象としており、施設の改修工事のための費用や、こどもが活動する場以外の場での対策費用は補助対象としておりません。
項目別には以下のとおりで、これ以外については別途ご相談ください。【事故防止】
・活動の場が屋外の場合も、事故防止や事故対応に資するものは対象となりますが、原則日中のこどもの活動に関わる費用に限られます。また、例えばAED等のリース費用については、補助金の申請を行う年度の支払分以外の年度は対象になりません。【防犯】
・窓の補助錠や、防犯フィルムの貼付けなども対象になります。
・こどもの個人情報保護のためのシュレッダーや、PC用のセキュリティソフトの購入費も対象となります。【防災】
・緊急時用の救急セット、非常用簡易トイレ防災ヘルメットなどは対象となります。
・防災セットについては「非常持出用の基本的なキッド」を対象としております。個別の食料や衣類・寝具などは、防災時と日常時の使用確認が困難であることから、原則対象にしておりません。 -
認証区分毎の補助上限額は、開所⽇数や利用人数に応じ、さらに区分毎の上限が設けられていますが、「開所⽇数」と「利用人数」の算定の仕方等はどのように考えればよいですか(申請⽇時点でよいでしょうか)?
補助上限額を判断する「基本開所日数(週当たり)」及び「実利用人数」ですが、交付申請時は、申請前年度の実績や申請年度の状況等を踏まえて申請年度の見込みを算出します。また、実績報告時には、申請年度の実績によりその交付額を確定します。
いずれも、月別の数値を平均した値で算出してください。 -
「安心・安全対策費」は、毎年申請が可能ですか?
補助対象経費の区分「事故防止、防犯、防災」ごとに申請は1回限りとし、申請をしていない区分については、次年度以降に上限額の範囲内(居場所支援型:15万円、学び支援型:45万円)で申請が可能です。
(学び支援型の場合の例:1年目に「事故防止」で35万円申請した場合、2年目以降に「防犯」及び「防災」で10万円の範囲内で申請可能)
利用するこどもの安心・安全を高める緊急的な措置として補助率を10/10としており、この機会に積極的かつ早期のご活用をお願いいたします。 -
週当たりの基本開所日数について、夏休みなどの長期休暇はどのように考えればよいですか?
週当たりの基本開所日数は、長期休暇を除いて考えてください。
以下の場合が考えられます。【7月のうち7月15日~7月31日までが夏休みの場合】
7月は7月1日~7月14日の間の週当たりの基本開所日数としてください。【7月はすべてが夏休みの場合】
7月を除いた11か月分で平均値を算出してください。
※その場合、週当たりの基本開所日数及び実利用人数は「-」として、備考へその旨記載してください。 -
フリースクール事業の他に事業を行っている場合は、どのように記載すればよいですか?必ず別紙5を使用しなければなりませんか?
他事業を行っている場合は、他事業とフリースクール事業のすみ分けをしていただき、フリースクール施設全体の収支(支出は、補助対象外を含むすべての経費等)を記載してください。
既存の根拠資料等がある場合は、提出の省略が可能です。 -
前年度の利用者名簿は、毎年提出しなければなりませんか?
2年目以降の申請では提出不要です。
-
どのような場合に変更交付申請が必要ですか?
以下の場合には変更の交付申請が必要となります。
- 補助事業の目的の達成に支障をきたすような事業変更であって、補助金の増額を伴うもの
- 補助対象経費の20パーセントを超える増額又は減額
-
年度末まで本事業(運営)を⾏っていますが、補助⾦事業の実績報告書は、要綱の定めにより事業実施年度中に提出しなければなりませんか?
申請年度末(3/31)までの事業実績を、翌年度の4/10までの日付で所定の様式にて提出(実績報告)してください。当該日付以降の日付となっているものは受理できませんので、ご留意ください。
ただし、補助事業の完了又は廃止のあった日から起算して 20 日を経過した日が上記より早い場合は、その日までの実績報告が必要です。
-
実績報告書にどんな添付資料を添付する必要がありますか?
各経費の領収書の写し、活動の様子が分かる行事概要や明細、写真などを添付していただくことになります。
書類の審査又は必要に応じ現地調査による確認を行う場合がありますので、対象者には別途ご連絡します。
領収書は、「宛名(施設名のものに限る)、発行日、購入品目及び金額」が確認できるものとしてください。
-
補助金交付要綱10の「概算払い」とは何ですか?必ず請求しないといけませんか?
「概算払い」とは、補助金事業の完了後に精算することを前提として、交付決定以降であれば事前に補助金額を概算で交付できる仕組みです。
交付決定額の8割(千円未満の端数は切り捨て)を上限に、年2回を限度として概算払い(概算払い請求書の提出)を行うことができます。
必ず請求しないといけないものではありません。 -
帳簿等の書類の保管はどのようにすればよいですか?
補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業終了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保存してください。なお、事業終了後の完了検査の際に、当該事業年度分の帳簿及び証拠書類を確認させていただくとともに、証拠書類がない支出については、補助対象経費から除外させていただくことがあります。